I make a fire. She begin to sing a song. 薪ストーブは歌う
山暮らしは秋。色づいた山桜の葉が庭に降ってる。鹿が鳴きはじめた。
「おしなべて ものを思わぬ者にさえ
心をつくる秋の初風」(西行)
南瓜とメロンを収穫した。霜降る前に鷹の爪とピーマンを取り込んだ。

いいぞ! アンコールが燃えはじめた。
薪ストーブが燃えない夏は手持ち無沙汰だ。
で、近所の川で夏を釣り暮らすことになるんだ。
落葉松の薪がはぜて、アンコールが歌ってる。
レモンイエローの炎が踊ってる。
ケトルの湯がたぎっている。
薪は適材適季。
こんな健やかな季節には針葉樹を燃やすのがいい。
ファイヤーウッドとしての落葉松はB級だが、B級であるが故の美徳もある。
火力が弱く火持ちがしないので、部屋が暑くならない。
落葉松の火ははぜて飛び散る。
でも、その音は薪ストーブが奏でる音楽なんだ。
ものは言いよう。
「きみの笑顔は野菊が咲ているみたいだ。厚化粧の薔薇より素敵だ」。
秋の薪ストーブは、ファイヤースクリーンで暖炉の優雅さを楽しもう。

薪ストーブが燃えると、心落ち着く。
日々の暮らしに心地いいメロディーが流れる。
薪ストーブはメロディアスなアダージョを奏でる。
北欧やロシアの音楽にアダージョの名曲が多いのは、暖炉や薪ストーブのある暮らしがそこにあるからだ。
薪ストーブは、日々の食生活に変化をもたらす。
プロパンガスのレンジで大きな馬鈴薯を茹でる気がしない。
40分かかるからね。ガス代が気になって冷や汗が出てくる。
「きみのビールの代に比べれば知れてる」という意見もあるが、それはまた別の話だ。
ストーブトップのケトルや深鍋でたっぷりの湯がたぎっている。
何をどう調理して食べればいいのか、ということを薪ストーブが教えてくれているんだ。
Good bye fast food.
プロパンガスのコストから解放されて、二酸化炭素排出の罪悪感からも解放されて…
何時間もかかる煮込み料理をせいせいと調理することができる。
ストーブトップで湯が沸いていないのは、不便よね。
好きな紅茶がすぐに飲めない。蕎麦やパスタを茹でるのが嫌になっちゃう。
ストーブが燃えない夏は、何に付け台所のガスレンジ頼み。
秋になってストーブが燃えだして、薪ストーブの便利さに敬礼!
炉室の熾き火的グリルファイヤーに感激!
そして、ファイヤーウッドに心からの感謝!
.jpg)
話は違うが、なんだか閉塞感が漂う時代になってきた。
窓のない部屋とトンネルが嫌いだ。
閉じ込められたら、逃げようがないからだ。
人だって動物だって鳥だって、いざというときには逃げ出してしまえそれでいい。
「待てー」なんて声は背中で聞き流して、脱兎のごとくに逃げちゃえばいいんだ。
逃げるが勝ちさ。
閉塞されるのはよくない。閉じて塞がれるのは最悪だ。
笑えなくなったような気がする。それが、寂しい。
気が合う者達との、心底からのくすくす笑い。
Cosmic giggle.
それは、同じ時代同じ社会を共有してきた者達との連帯的笑いだ。
くすくす笑いは、文化なんだ。
そういう笑いを共有できる機会が失われようとしている。
それは、「明日もまた自分たちの笑いを共有しながら明るく生きていくんだ」という前向きな姿勢の衰退だ。
笑えない時代はつまんない。だって、面白くないから笑えないんだもん。
本当のことには口にチャックして、いい子ぶってる者達だけがはびこってる時代なんて面白くない。
どうしよう……? わかった! 取り敢えずは、薪ストーブに火を起こそう。
.jpg)
JAIME DE ANGULO(ジェイム・デュ・アングロ。1887ー1950年)の笑える詩を紹介します。
彼は、1900年代の初頭にキャリフォルニア・ピットリバー・インディアンと一緒に暮らした。
ジェイムはカウボーイ、医者、人類学者、言語学者、音楽家、そして、詩人だった。
彼は、アカデミズムに馴染まない人生を生きた。
狐は独りで暮らしていた。現世はなかった。そこいらじゅうが水浸しだった。
“どうすりゃいいんだろう?”
狐は独り口した。狐は答えを捜すかわりに、歌いはじめた。
“ぼくは誰かに会いたいんだ”
彼は空にむかって歌った。そしたら、コヨーテに会った。
“誰かに会いたいとおもっていたんだ”
狐は言った。
“何処へ行くつもりなんだい?”
コヨーテが訊いた。
“ぼくは誰かを捜そうとおもって、そこいらじゅうをほっつき歩いたんだ。
で、ぼくはここでちょっと悩んでたんだよ”
“そうだったの。だったら二人で一緒に行こうよ”
“そうとも! でも、どうしようか?”
“わかんないよ”
“わかった! 世界をつくってみようよ”
“でも、それからどうすりゃいいんだろう?”
コヨーテが訊いた。
“歌うんだよ”
狐が応えた。
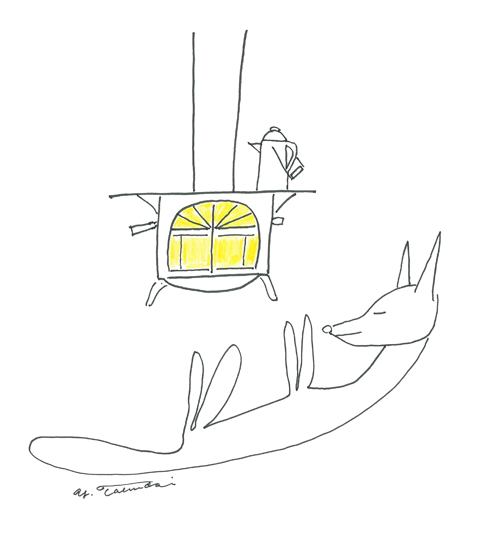
Photoes & Illustration by Yoshio Tabuchi